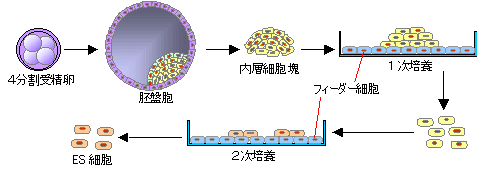人工的操作によって細胞を加工したり,胚細胞(発生初期の細胞)を培養する技術である。細胞工学は,遺伝子工学,バイオテクノロジーと並んで,21世紀を支える重要な科学技術である。
|
 |
 |
|
- 自然界では受精の際に細胞融合がおきるが,異種細胞間では一般に自然に融合することはない。細胞融合は,人工的に2つの異種細胞どうしまたは細胞質や核を融合する技術で,通常の交配では交配不可能な種同士の形質を兼ね備えた細胞種の作成を可能にした。
センダイウィルス(HVJ)は赤血球の溶血を引き起こすウィルスであるが,細胞を融合する作用があることが発見された(岡田善雄,1957年)。その後,高濃度のポリエチレングリコールを含む培養液中で培養して細胞の融合を促進する方法や電気パルスを用いる方法などが開発され,細胞融合が手軽に行えるようになった。このようにして得られた雑種細胞は、両種の遺伝子を持っているので、この細胞を培養して植物体を分化させると、両種の形質を合わせもった雑種細胞が得られる。現在では新品種の開発や品種改良はもとより,有用微生物の改良,単クローン性抗体の作成など多岐にわたって実用化されている。
 細胞融合剤
細胞融合剤
-
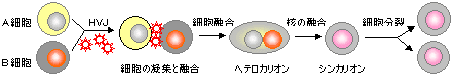 |
| センダイウィルスによる細胞融合 |
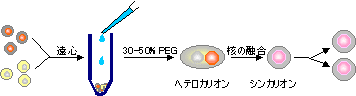 |
| [-CH2CH2O-]n |
ポリエチレングリコールによる細胞融合 |
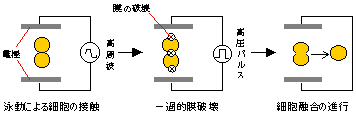 |
電気穿孔法による細胞融合
(電気穿孔法は遺伝子導入にも利用される) |
 細胞融合の利用
細胞融合の利用
-
 農業への応用
農業への応用
- 植物細胞の融合では,まず細胞をばらばらにするために細胞間を埋めているペクチンをペクチナーゼで分解する必要がある。さらに,"細胞壁"が邪魔になるため,セルラーゼなどの酵素を使って細胞壁を除き,細胞膜のみで囲まれた状態(プロトプラスト)にする。これらの技術が開発されたおかげで,異植物同士の細胞融合が可能になり,この分野に関する研究・実用化が大きく飛躍した。
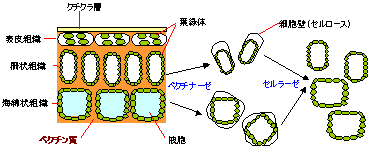 |
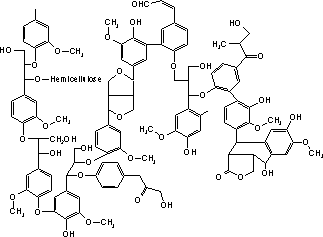 |
植物細胞のプロトプラスト作成法(上)と,
植物細胞の成分であるペクチンの構造(下) |
最初,じゃがいも(potato)とトマト(tomato)を融合してつくられた植物,ポマト(pomato)が有名になったが,地上部は両方の中間的な形質が現れてトマトのような実はならず、地下部もごぼうのような根が伸びるだけで実用的な代物ではなかった。野菜や果樹など植物で実用化されたものはまだないが,商品化を目指し開発が進められている。
| 細胞融合で開発された植物 |
・オレタチ: オレンジとカラタチ
・ハクラン: ハクサイと赤キャベツ
・千宝菜: キャベツと小松菜
・ベンリ菜: 小松菜とチンゲン菜
・トマピー: トマトとピーマン
・シューブル: 温州ミカンとネーブル
・グレーブル: グレープフルーツとネーブル |
 医療への応用(単クローン性抗体の作製)
医療への応用(単クローン性抗体の作製)
- 抗体産生細胞と癌細胞を融合させて、単一の特異性をもつ抗体(モノクローナル抗体)を大量に、細胞培養で生産できるシステムが開発された。単クローン性抗体は化学的に純粋な抗体で,従来の動物に免疫して得られる不均一な抗体よりも一般に力価が高く,また,特定の抗原決定基に向けられた特異性を持つ。
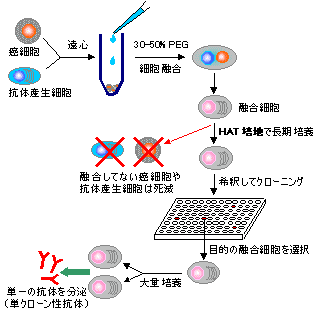 |
【HAT培地】
ヒポキサンチン(salvage合成によりプリン塩基を生じる),チミジン(salvage合成によりピリミジン塩基を生じる),およびアミノプテリン(PRPP合成阻害剤)を加えた培養液。 |
細胞融合に用いる癌細胞はヌクレオチドのsalvage合成能(例えば,チミジンキナーゼやHGPRT)を欠くものが用いられる。融合細胞と癌細胞はともに,長期培養に耐える。しかしながら,HAT培養液中にはアミノプテリン(PRPP合成阻害剤)が含まれているので,ヌクレオチドのde Novo合成がブロックされる。癌細胞は両方の経路が絶たれるために,培養中に死滅する。また,正常の(融合してない)抗体産生細胞は寿命が短いため,じきに死んでしまう。
一方,融合細胞は抗体産生細胞由来のsalvage合成能によりヌクレオチドをつくれるので,HAT倍地中でも生き延びる。 |
| モノクローナル抗体の作成 |
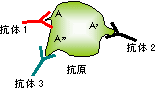
抗原決定基と抗体 |
抗原は一般に複数の抗原決定基をもつ。たとえ純粋な抗体を動物に免疫しても,つくられる抗体は不均一なものとなる。
モノクローナル抗体は,ただ1つの抗原決定基に向けられたものである。 |
現在,単クローン性抗体は診断薬や治療薬および学術研究用に、モノクローナル抗体が広く利用されている。従来、マウスの細胞が利用されていたが、治療用として利用する場合,体内で免疫反応を誘発するという問題があった。そこで,ヒト型のモノクローン抗体の開発が注目されている。モノクローナル抗体は今や手軽に開発できるので,多くの企業が開発を進めている。
 醸造への応用
醸造への応用
- 醸造分野では、酵母や麹菌の育種に広く応用されており、パンや日本酒、焼酎、ワインなどの生産に実用化されている。
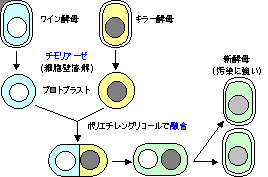 |
| ワイン酵母の改良 |
 染色体遺伝子の解析
染色体遺伝子の解析
- ヒト体細胞とげっ歯類の細胞を融合すると,ヒト由来の染色体が徐々に抜け落ちていく。これを利用して,多くのヒト遺伝子座が決定された。
 特定のタンパク質の生産
特定のタンパク質の生産
- 特定の正常細胞を癌細胞と融合すれば,融合細胞によって複合タンパク質をつくることができる。
 細胞融合による核や細胞質の注入
細胞融合による核や細胞質の注入
- 細胞融合を利用すれば,特定の細胞の核や細胞質を別の細胞に注入することができる。
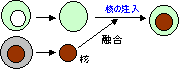 |
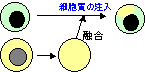 |
| 細胞融合による核や細胞質の注入 |
- 顕微鏡下,細胞に物質を注入したり,核や細胞小器官を取り除いたりする技術を細胞内注入技術(ミクロマニピュレーション)という。
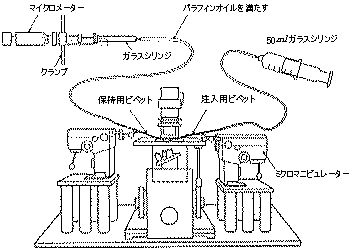 細胞内注入装置
細胞内注入装置
個体発生は1個の受精卵(胚細胞)が細胞分裂と分化をくり返し,各種臓器や器官を形成する。これら胚細胞の培養や遺伝子操作などを用いる技術を発生工学と呼ぶ。発生工学は個体発生の過程の解明や遺伝子解析などに重要な手段を提供しているだけでなく,最近樹立されたヒトの胚細胞株は,将来の医療に大きな影響を与えるであろう。
 クローン動物
クローン動物
- これまで,胚細胞の培養技術を用いて,種々のキメラ動物,遺伝子導入動物(トランスジェニック動物),およびクローン動物が作られてきた。キメラ動物は免疫学的研究に大きな貢献をした。また,遺伝子導入動物は外来性の遺伝子を導入し形質転換を目的とした機能獲得性の変異動物で,特定の遺伝子の機能をin vivoで解析する有効な手段となっている。
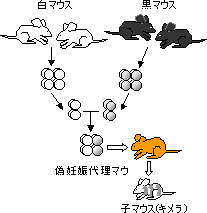
キメラ動物の作成 |
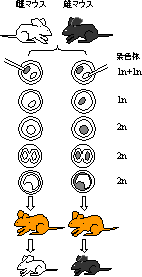
クローン動物の作成 |
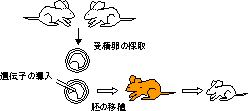
トランスジェニック動物の作成 |
これらは動物の胚細胞を利用したものであったが,1996年,英国ロスリン研究所で体細胞を用いたクローン技術によって,哺乳類動物としては世界で初めてクローン羊「ドリー」が誕生し,世界中を驚かせた。体細胞クローン動物は,雌の卵細胞から核を取り除いた後,複製元となる別の動物から体細胞を採取して核を取り出し,核を取り除いた卵細胞に移植してつくられた。
その後,クローン牛もつくられ,新しい家畜の改良法として畜産分野で大きな期待を集めている。また,絶滅に瀕した動物をクローン化で救済するアイデアも出されている。
 胚性幹細胞の樹立と再生医療
胚性幹細胞の樹立と再生医療
- 受精卵が個体へと発生する初期の胚には,あらゆる細胞へと分化する能力をもつ細胞があり,胚性幹細胞(Embryonic
Stem cell,ES細胞)と呼ばれている。また,生殖細胞以外の細胞で,いくつかの細胞に分化できる幹細胞が成体でも存在する。
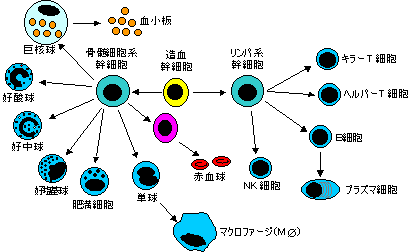 |
| 造血系幹細胞 |
 ヒトの胚性幹細胞
ヒトの胚性幹細胞
1998年,胚性幹細胞(ES細胞)と胚性生殖幹細胞(Embryonic Germ cell,EG細胞)がヒトから樹立されたことが発表された。ES細胞は最初,マウスにおいて細胞株として樹立が報告されたのをはじめとして,数種の動物において樹立されている。ヒトのES細胞は受精後5〜7日目の胚盤胞の内層細胞(内部塊細胞)からの細胞を培養することにより樹立された。
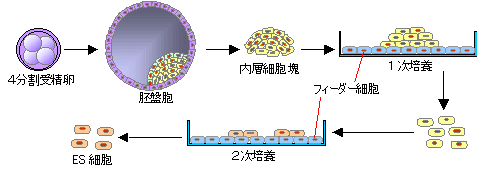 |
| ES細胞の樹立 |
一方,EG細胞は,将来精子や卵になる細胞(始原生殖細胞)から樹立される細胞で,ES細胞とほぼ同じ性質をもつことがマウスの研究から分かっている。ヒトの場合,EG細胞は妊娠5〜9週の死亡胎児から始原生殖細胞を取り出して,ES細胞と同様に培養することにより樹立された。
これらヒトの細胞は,将来的には移植用の細胞,組織,臓器として医療に応用することが期待されている。また,胚性幹細胞は全能性をもつことから,ヒト胚性幹細胞を使用することは,ヒトを対象とした生命科学の基礎研究においても有用であると考えられる。さらに,ヒト胚性幹細胞が化学物質などの影響を受けやすい性質を利用して,医薬品の効果の判定や毒性試験などへの応用も考えられる。これらの進歩が,再生医学・医療など,将来の医療を大きく変えようとしているのが現状である。と同時に,これまでの生命観を大きく変えることにもなるであろう。
欧米ではすでに多くの再生医療ビジネスが起こっており,患者への治療に活かされている。日本でもようやく皮膚や骨の再生を目指すベンチャー企業が創業され始めた。
【体細胞クローン動物とテロメア】
体細胞クローン動物であるドリーは、染色体の両端のテロメアの長さが同年齢の羊よりも20%ほど短いことがわかり,老化が早く寿命が短いのではないかと疑いが出てきた。ドリーの場合は、6歳の羊の体細胞の核が利用されたので,年齢相応に短くなったテロメアをもって生まれたのではないかというわけである。しかし,2000年に誕生したクローン子ウシのテロメアの長さは通常の子ウシと全く同じであったという。クローニングの過程でクローン細胞の"加齢時計"がリセットされるのかも知れない。 |






 細胞融合剤
細胞融合剤
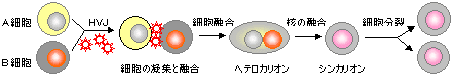
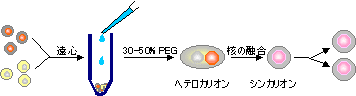
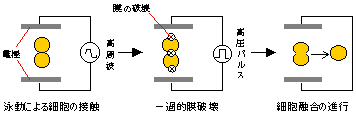
 細胞融合の利用
細胞融合の利用
 農業への応用
農業への応用
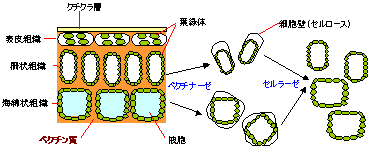
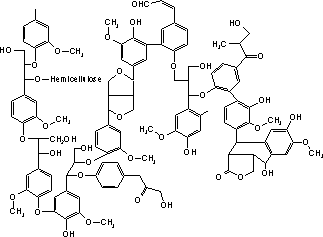
 医療への応用(単クローン性抗体の作製)
医療への応用(単クローン性抗体の作製)
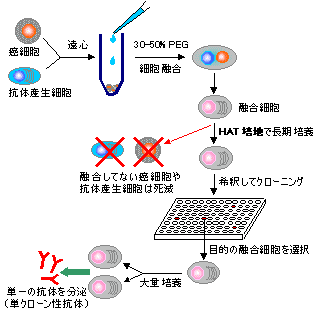
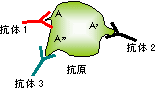
 醸造への応用
醸造への応用
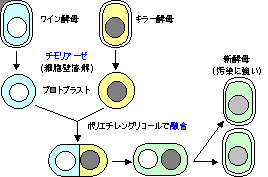
 染色体遺伝子の解析
染色体遺伝子の解析
 特定のタンパク質の生産
特定のタンパク質の生産
 細胞融合による核や細胞質の注入
細胞融合による核や細胞質の注入
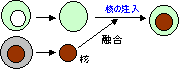
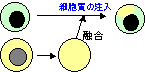
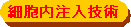


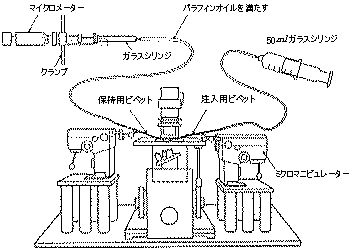 細胞内注入装置
細胞内注入装置


 クローン動物
クローン動物
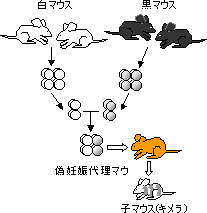
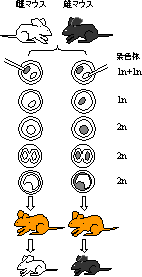
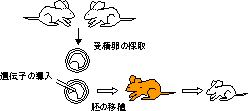
 胚性幹細胞の樹立と再生医療
胚性幹細胞の樹立と再生医療
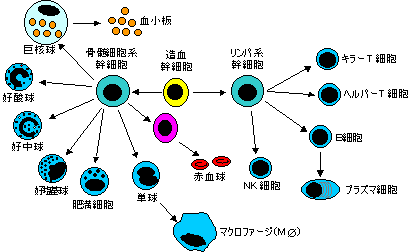
 ヒトの胚性幹細胞
ヒトの胚性幹細胞